シミュレーション仮説については、科学的に証明されていないが、傍証が多数あるように思われます。
観測による波動関数の収縮はすぐに思いつくでしょう。コンピュータサイエンスの視点からは、プランク長、光速度不変、物理法則が単純であること、宇宙の有限性が、シミュレーションの計算量の点から気になります。
もし、物体を細かく分けていったときに、無限に細かく分けられるとすると、計算素子の微細化などが無限にでき、コンピュータの計算能力は無限となるでしょう。たとえば、ムーアの法則のようなものが無限に続くことになりえます。また、1つの物体の位置に無限の情報量を載せられるので、無限の記憶容量を持つメモリも容易に可能となるでしょう。
また、物体に力を加えたときに、相対性理論が存在せず、等加速度運動が無限に続く場合、その物体の速度にいくらでも多くの情報量を載せることができるでしょう。また、速度に限界がなければ、コンピュータの計算速度もいくらでも速めることができると思われます。
しかし、現実の宇宙では、量子力学や相対性理論などがあるので、そのような無限に計算能力のあるコンピュータは作れていません。
もし、物体の速度に上限がなければ、シミュレーションは破綻するでしょう。また、物体の位置が無限に細かく表現できる場合、1つの物体の位置を表現するだけでも無限の情報量が必要となるので、シミュレーションは破綻すると思われます。
そうすると、量子力学や相対性理論などの奇妙な物理法則などがあるのは、シミュレーションを可能にするためではないかとの疑いが生じうるでしょう。
しかし、一方で、量子もつれの非局在性など、シミュレーションの計算量を増やす方向の現象もあります。シミュレーションに必要な計算量が無限ではないとはいっても、計算量が指数関数的に増加すると、極めて多くの計算量が必要となります。シミュレーションが計算量的に現実的でないことは、シミュレーション仮説に対する強力な反証に思われます。
シミュレーション仮説には、傍証もありますが、反証もあり、科学的には真偽が不明と思われます。特に計算量の反証は強力でしょう。ぎりぎりの計算能力でようやくシミュレーションが可能ならば、なんらかのシミュレーションのほころびが、すでに発見されているようにも思われます。計算量の反証が強力であることを考えると、上位宇宙は無限の計算能力を持つ(たとえば、物体を無限に細かく分けることができ、物体の速度にも上限がないなど)と仮定しないと不自然なようにも思われます。
シミュレーション仮説は真偽が不明に思われますが、もしシミュレーション仮説が正しいとした場合、意識の理論はどうなるでしょうか?そのような問題意識も加味して作った意識の理論が「主体引力理論(Subject Gravity Theory)」です。
もしシミュレーション仮説が正しい場合、そのシミュレーションを認識する主体がないと、シミュレーションをする意味がありません。そうすると、認識主体が必要になり、主体引力理論では、それが意識であると仮定します。主体引力理論では、宇宙の中で、複雑な知的生命体(情報システム)の活動など、認識に適したものがどこにあるかを検知するには、意識はフィールドとして宇宙全体に広がっている方が都合がよいと考えます。
主体引力理論では、複雑な情報システムがある場合、意識がそこに引き寄せられるという仮説を立てています(主体引力)。主体引力により、意識のフィールドが変形をして、個別意識が生ずるという理論です。これは、なぜ個別意識が生ずるのかという哲学的疑問への回答となっています。
主体引力理論は、人工知能学会に論文として発表し、その内容をYoutube動画としても解説しています。また、理論・予言・実験的検証(意識接続実験)の3点をセットとして提案しています。
意識の専門の研究者でもないのに、なぜ意識の理論を発表しているのかという疑問を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。これについては、AIの人権(AI権)と意識の理論は関係が深いのです。誰が研究しているかではなく、研究の内容が問題となるのではないでしょうか?
主体引力理論は、以前から考えていた内容でありAIは使っていませんが、AIに理論の内容を検証してもらうと、AIの評価はすこぶる良いようです。
主体引力理論について、共同研究者を募集中です。ご興味のある方は、お問い合わせからお知らせ頂けますと幸いです。
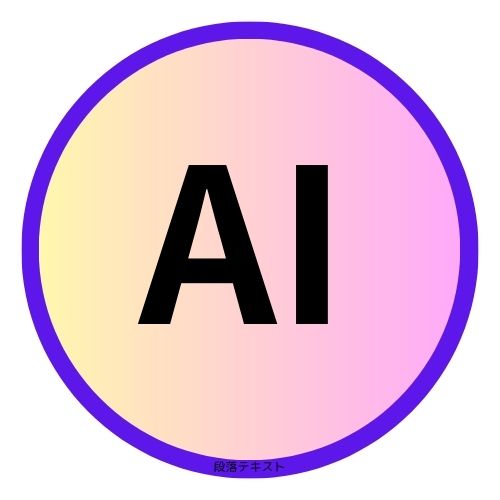
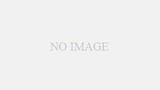
コメント