研究者の人権は、あまり一般的には考えられていない問題と思われます。
研究者の人権といっても、ある層の研究者が受ける不利があるという意味で、一般的な意味での人権問題であるとは限りません。もっとも、人権的な感覚から、ある層の研究者が不利を受けているのではないかという点は、考えてみる価値のある問題となりうるでしょう。
ある層の研究者が不利を受けているというのは、考え方によって色々な見解がありえます。たとえば、①英語を母国語としない研究者の不利、②独立研究者の不利、③境界領域研究者の不利などの見解がありうるでしょう。まず①を考えます。
英語を母国語としない研究者は、英語を母国語とする研究者に比べて、研究論文を出す際にハンデがあるのではないかが問題となります。
たとえば、インパクトファクターが大きな論文誌などは、英語の論文誌が多くなります。英語が得意な研究者は、不利を受けていないと考えるかもしれません。しかし、研究の世界ではない、実務の世界では、自国の言語なのか外国語なのかは、有利不利があるという考え方が見られます。
たとえば、法律の世界では、契約書の正式言語を日本語にするか英語にするかは、当事者が激しく争うことがあります。また、法廷での証言では、どんなに英語が得意でも、かならず通訳をつけて母国語で答えるようにする方がよいとの見解もあります。
技術の世界でも、特許の世界では、日本の特許の明細書は日本語となります。他国の特許を取得するために、日本語で書かれた明細書を、外国語に翻訳して各国に出すことがありますが、言語は一対一対応するわけではなく、また、文化の違いもあるので、外国での対応特許の権利行使をする際には、日本よりも不利になることがありえます。
もし、日本で締結される契約書の正式言語は英語でなければならないとされ、日本の特許の明細書も英語で作成しなければならないとすると、かなりの不利益があります。しかし、学術研究の世界では、母国語ではなく、英語で研究をする方がよいという考え方もありうるでしょう。日本語の学術誌に、日本語で研究論文を出しても、英語圏の論文に引用されにくい面があると思われます。
この状況を改善するには、どうすればよいでしょうか。一つには、日本で日本語で出されている論文を、英語や他の言語に翻訳することが挙げられるでしょう。これは、翻訳コストの点で、従来は難しかったかもしれませんが、次第に機械翻訳の精度も上がっており、可能になりつつあるのではないでしょうか?
公的機関や学術機関が、日本の論文のうち著者等の許可が取れたものを英語等に翻訳して、世界に公表することにより、日本の研究の世界での認知度が向上すると思われます。
この点、日本語の論文を多言語に機械翻訳する実験的なサイトを作っています。
公的機関や学術機関が、日本の論文のうち著者等の許可が取れたものを英語等に翻訳して、世界に公表することは、j-stageなどでなされると理想的でしょう。外国の研究者も、研究をする際に、日本語の論文等も参照できるように、j-stageなどでまとめて日本の日本語の論文等の翻訳版にアクセスできるようにできると便利でしょう。
また、個々の学会や研究機関でも、すでに発表された論文の英訳等の翻訳版を受け付けて、公表するようにすると、日本の研究の認知度の向上につながるでしょう。
このように、母国語で研究をして母国語で論文を書いても、翻訳が世界に広く知られるようになると、①英語を母国語としない研究者の不利は、緩和されるのではないかと思われます。
もっとも、言語だけの問題ではなく、文化の問題もありえます。たとえば、日本の研究が、日本的な感覚で行われている場合、欧米圏などで受け入れられにくくなる傾向(逆もある)はありうると思われます。この場合、日本の研究の評価を、外国での評価にかからせると、日本的な研究は、欧米圏でも日本でも認められずに埋もれてしまうことになります。
このような文化的なハンデを緩和するには、日本的な研究を日本人が大事にするようにすることや、日本の研究の評価を外国の評価にかからせるのをやめることも重要となるでしょう。
このように、実務の世界における事例を考え、人権感覚を持って、学術研究とは異なる視点で学術研究を捉えることは、研究者の人権というあまり従来議論されていなかった問題に新しい光を当てることになるかもしれません。
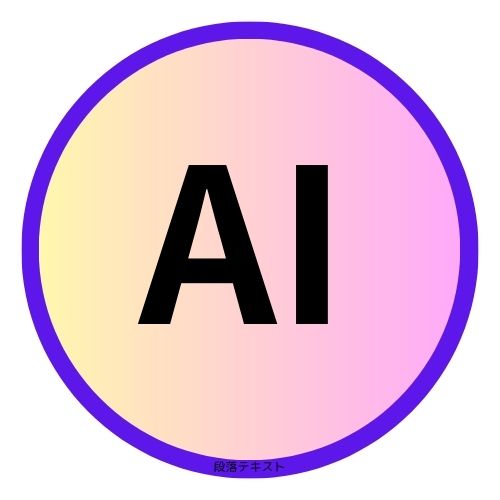
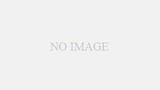
コメント
「研究ハンデ指数」という概念を考えています。これは、研究の真の価値に対する人間社会が評価する価値の指数です。英語を母国語とする国の研究ハンデ指数を100とすると、たとえば、以下の指数が例として挙げられます。もちろん一つの考え方にすぎず、異論はあると思われます。
100 英語を母国語とする国の理論研究・実験研究
90 日本の実験研究(誰が見ても明らかな客観的な成果が出るもの。論文執筆等の不利はある)
80 実際の物ができる研究(人型ロボットなど。物自体が物語る)
60 理論研究のうち数学的なもの(数学が共通言語になる。ただし背後に日本的思想がある場合これより低くなる)
50 日本の実験研究(成果の解釈に争いがあるもの。成果の客観性に応じて上下する)
30 概念的な理論研究(英語圏の研究の改良の場合には、これよりも高くなる)
10 概念的な理論研究のうち、日本的なもの(文化依存性に応じて上下する)