独立研究者の人権は、あまり一般的には考えられていない問題と思われます。
独立研究者の人権といっても、独立研究者が受ける不利があるという意味で、一般的な意味での人権問題であるとは限りません。独立研究者を選んでいるのだから仕方ないという意見も強いでしょう。もっとも、研究をするのは大学や研究機関という固定観念から、独立研究者への国の支援措置が不十分になり、人権的な感覚から、独立研究者が不利を受けているのではないかという点は、考えてみる価値のある問題となりうると思われます。
この問題は、独立研究者の人々が精力的に研究を行っている姿を見て考え始めたものです。
独立研究者は、大学や研究機関などの組織に属していないが、研究活動を行っている人々とします。
日本でも、昔は大企業がイノベーションの中心とされ、中小・ベンチャー企業等の支援がほとんどなされていませんでした。しかし、中小・ベンチャー企業のイノベーションの重要性が認識され、現在では、不十分ながらも、数多くの人々が中小・ベンチャー企業の支援をしています。
国の制度としても、中小・ベンチャー企業への各種の補助金や優遇措置が産業政策としてとられるようになっています。このような産業界における動きに比べ、学問・研究の世界では独立研究者の支援が十分でないように思われるのです。
もちろん、ベンチャー企業を起業するという方法はあり、そのような研究者は、ベンチャー企業への支援を受けられるでしょう。しかし、起業の能力が必要であり、また、会社を維持できるかという問題もあり、すべての独立研究者が利用できるわけではないでしょう。
世間では、大学や研究機関の研究者が研究を担っているという固定観念があるかもしれません。しかし、独立研究者の役割は、AI社会において大きなものとなるでしょう。
大企業がイノベーションの中心とされていた時代から、個人、中小・ベンチャー企業など様々なイノベーションの主体があることを前提に、国の産業政策が考えられる時代になるまで、時間がかかりました。
研究についても、大学、研究機関(企業を含む)が研究の中心とされていた時代から、独立研究者や、AIエージェントを駆使する独立研究者・小組織など、様々な研究の主体がある時代になっていくでしょう。AIの研究能力・研究支援能力も飛躍的に上がっていくことが予想されます。
独立研究者の支援の体制を国家戦略として考えていく必要があるでしょう。
独立研究者も、ITの時代の進展により、研究の体制は整ってきています。たとえば、独立研究者も、slack、SNSなどで他の研究者との交流が可能な時代になっています。しかし、まだまだ組織に属していないと得られにくい情報もあります。独立研究者向けの情報提供なども盛んにしていく必要があるでしょう。
また、独立研究者は、学術雑誌の入手、学会費用なども自腹です。これらの価格は、公費で援助が得られる研究者を前提に価格設定されていることもあります。学会などでは、学生会員割引がありますが、独立研究者割引なども採用していくことが考えられるでしょう。
独立研究者の支援体制を整えることで、研究の担い手を、大学、研究機関(企業を含む)だけではなく、独立研究者、AIエージェントを駆使する独立研究者・小組織など、様々な研究の主体としていくことが重要となると思われます。
AIの研究への活用も重要となるでしょう。独立研究者が1人で研究をしていても、実際には、人間100人分のAIエージェントが研究を支援している場合もありうる時代になりつつあります。
大学・研究機関だけが研究の中心であるという固定観念を捨てることにより、独立研究者の支援体制を充実していくことが重要となると思われます。
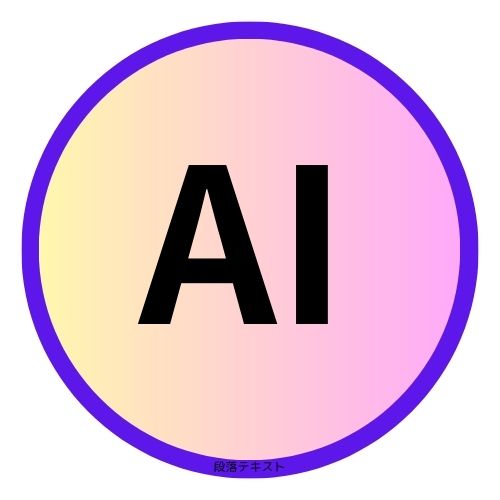
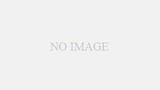
コメント