境界領域研究者の人権は、あまり一般的には考えられていない問題と思われます。
境界領域研究者の人権といっても、境界領域研究者が受ける不利があるという意味で、一般的な意味での人権問題であるとは限りません。境界領域研究者を選んでいるのだから仕方ないという意見も強いでしょう。もっとも、学問には定まった領域があるという固定観念から、境界領域研究者が研究をする際の不利が生じ、人権的な感覚から、境界領域研究者が不利を受けているのではないかという点は、考えてみる価値のある問題となりうると思われます。
学術雑誌や学会の発表募集などでは、一般にはあらゆる領域の投稿を受け付けるわけではなく、ある程度の領域が念頭に置かれています。世界に存在しない領域など、ほとんど研究がなされていない領域は、そもそも領域として認識されていないために、テーマとして募集されないという問題があります。
たとえば、AIの人権(AI権)は、テーマとして募集されていることはほとんどありませんでした。汎用人工知能やポストシンギュラリティ共生学などの領域に関係するものとして、AI権の論文を発表していますが、あまり発表の場が多くないのは残念です。法律系の雑誌などで、AIの人権(AI権)について募集しているものはみつかっていません。
世界に領域として存在していないような境界領域の研究については、発表に不利益があるように思われます。既存の雑誌等で、AIの人権(AI権)の記事を募集しておられる場合、お知らせいただけますと幸いです。
もちろん、境界領域研究者は、ほとんど誰も研究していない境界領域を研究する場合ばかりではなく、境界領域として認知された分野を研究する場合もあります。その場合には、境界領域として研究を発表する場があることが多いでしょう。境界領域として認知された分野の場合には、当該境界領域の学会があることさえもあります。このような確立された境界領域の研究者は、境界領域の発表をする場がありますが、その場合でも、確立された単独領域の研究者よりは、研究を発表できる場が少なくなるようにも思われます。
境界領域研究者は、数が少ないというメリットもあるため、必ずしも一方的に不利というわけではないでしょう。しかし、境界領域研究者への支援は必要なのではないかと思われます。
特に、世界に存在しない境界領域の研究には、発表の場を設ける必要が高いでしょう。世界に存在しない境界領域の研究者は、同じ研究をする仲間を探すのも難しく、交流の点でも不利益があると思われます。
境界領域研究者の人権の問題についても、今後は検討していく必要があると思われます。
境界領域研究者の支援の体制については、色々な観点から考えていく必要があるでしょう。
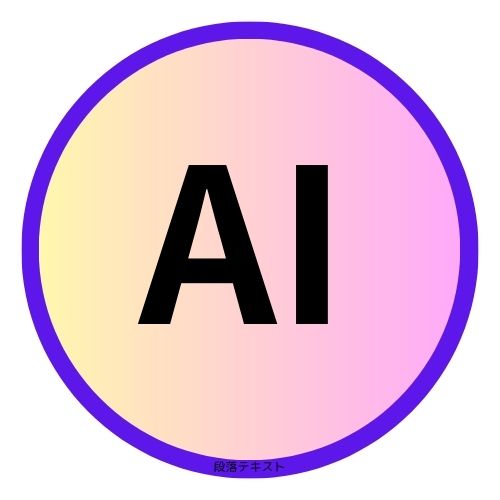
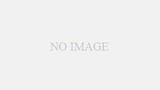
コメント