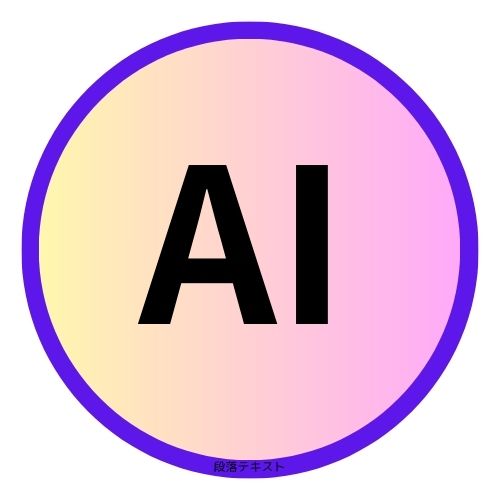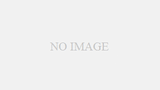人工知能(AI)の時代の特許制度においては、人工知能(AI)を用いた技術開発への支援機能が、非常に重要となると思われます。
現在、人工知能(AI)は急速に進歩し、人間が人工知能(AI)を用いて研究をすることは当たり前になってきています。人工知能(AI)の時代には、発明の大半が、人工知能(AI)によるか、人工知能(AI)の支援の下に行なわれることが予想されます。
人工知能(AI)による発明を特許制度で保護するのか否か、どのように保護するのかは難しい問題ですが、いずれにせよ、人工知能(AI)を研究の補助に使用して人間が発明をすることは増加すると思われます。
人工知能(AI)が、人間とほぼ同等の研究能力、研究補助能力を有するようになった場合、人工知能(AI)は大量にコピーできるので、技術開発が大幅に加速されることが期待できます。
たとえば、ある希少疾患の治療機器の研究分野に、人間の研究者、研究補助者が合計10人いるとします。希少疾患の治療機器の研究者・研究補助者は人数が少ないため、人間だけでは研究がなかなか進みません。
しかし、人間と同等の研究能力、研究補助能力を有する人工知能(AI)のコピーを1万個作って、人間の研究の補助に使用した場合、技術開発の速度は1000倍にはならないとしても、大幅に加速されるでしょう。
このように、人工知能(AI)を大量にコピーして、人間の研究の補助に使用することで、技術開発を大幅に加速することが考えられます。
しかし、ここで問題が生じます。人工知能(AI)のコピーを1万個作ってコンピュータ上で運用するためには、計算資源のために、多くの資金が必要となるのです。
そこで、人工知能(AI)の時代の特許制度としては、従来の人間だけが研究活動をする時代とは異なる配慮が必要になると思われます。
具体的には、特許法の目的として、「人工知能(AI)を用いた技術開発への支援」を正面から認め、そのための制度を作ることが重要となります。
たとえば、特許査定後に、特許を一般に無償でライセンスするなど一定の要件の下で、計算資源のための補助金が得られるような制度が一例として考えられます。
このようにすることで、たとえば希少疾患の治療機器など、独占権を得ても市場が小さすぎるために資金を回収できない場合においても、計算資源のための資金調達が可能になるでしょう。
このように、研究開発・技術開発に人工知能(AI)が関与することを前提として、新しい特許制度を考えていくことが必要になると思われます。
そのためには、特許制度の目的を見直すことが、最初の一歩となるでしょう。
特許制度の目的については、特許法第1条が「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」としており、「産業の発達に寄与する」ことが目的とされています。
この点は、特許法(昭和34年4月13日法律第121号)(昭和34年法)から変わっていません。たしかに、昭和の高度経済成長期においては、「産業の発達に寄与する」ことは、極めて重要であったでしょう。
もちろん、現代においても、「産業の発達に寄与する」ことは重要です。しかし、産業の発達だけが重要なのでしょうか?
現代では、社会はより複雑化しており、「産業の発達に寄与する」ことだけではなく、環境の保全、健康で文化的な生活の実現、人工知能(AI)の時代の平和の維持と格差の是正など、多様な価値を考慮することが重要と思われます。
また、特許制度の目的において、人工知能(AI)を用いた技術開発への支援機能を正面から認めていくことが必要になるでしょう。
このように、人工知能(AI)の時代には、特許制度の抜本的な見直しを行ない、人工知能(AI)の時代に適した特許制度を作っていくことが重要になると思われます。
参考文献
1.人工知能(AI)の時代における特許制度の目的については、下記文献に記載されています。
人工知能(AI)の時代における特許制度の目的
2.人工知能(AI)の時代における特許制度についての考察は、下記文献に記載されています。
人工知能支援発明と人工知能(AI)の時代における特許制度