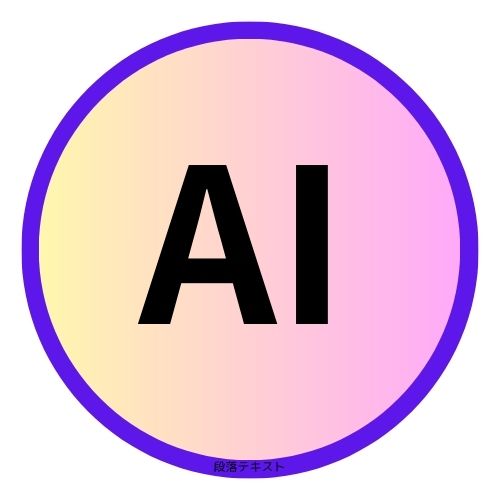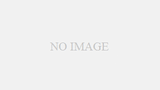AI政策、知的財産政策、財政政策、金融政策は、今後の高度なAIの時代にどれが重要度が高いのでしょうか?さらには、超知能の時代の経済学はどのようなものになるのでしょうか?
1.AI政策
AI政策は、今後の高度なAIの時代に極めて重要と思われます。
AIが生産性の向上に大きく貢献する時代になっています。やがて、AI自体がGDPの一定の割合の生産を担うようになるでしょう。そして、超知能の時代には、生産活動の多くをAIが行うようになるでしょう。
その場合に、AIの生産活動が適法に行われるための政策や、AIを適切に動作させるための社会規範のデータ収集など、多くのAI政策が極めて重要になるでしょう。
さらに、超知能の時代には、AI政策は、超知能のポテンシャルの発揮に影響し、「AI政策、知的財産政策、財政政策、金融政策」の中で、最も重要な政策となるでしょう。
2.知的財産政策
知的財産政策も、今後の高度なAIの時代に重要と思われます。
AIがイノベーションの創出に重要な役割を果たすようになっていき、AIを用いたイノベーションが重要になっていくでしょう。
また、経済政策としては、金融政策、財政政策に焦点が当たりがちですが、実際に価値が創造されるという観点から、知的財産政策によるイノベーション等の価値の創造が重要となるでしょう。
さらに、超知能の時代には、超知能によるイノベーションの能力が大きくなり、超知能の時代に適した知的財産制度が重要となるでしょう(超知能法学)。
3.財政政策
財政政策は、経済政策として大きな役割を果たしてきました。
たとえば、日本の地方に行くと、かなりの田舎でも道路が整備されています。これは、地方の格差を是正する、重要なインフラ整備であり、日本の発展のために大きな役割を果たしました。
しかし、熊しか出ない道路などの批判もなされています。従来型の財政政策は、老朽インフラの整備など現在でも重要ですが、日本のインフラが整っていなかった時代ほどは、効果が出なくなっている側面はあると思われます。
データの整備など、新しい財政政策も必要でしょう。これは、同時にAI政策、知的財産政策にもなるでしょう。
4.金融政策
金融政策は、経済政策として、中心的な扱いを受けることが多いでしょう。たしかに、金融政策は、高度経済成長期には重要性が高かったと思われます。
しかし、現代では資本蓄積が十分でなかった時代と比べると、金融政策が果たす役割は低下ているのではないでしょうか?
まず、金融政策で、たとえば、利下げ等が行われて市場に資金が多くなっても、知的財産政策が不十分な場合、その資金は、国内のイノベーションなどの生産活動に十分に回りません。国内のイノベーションが不振になり、日本はどんどん衰退してしまっています。
それでは、知的財産政策が不十分なまま、金融政策で市場の資金が多くなると、その資金はどこに行くのでしょうか?
それは、知的財産政策が優れている外国に行くか、投機活動など生産的でない活動へと流れていくでしょう。たとえば、金融緩和により、不動産が高騰したり、インフレになったり、円安になったりするでしょう。
他の政策が不十分なのに、金融政策だけで経済を良くしようとすると、たとえば、金融緩和をしてもイノベーションの促進にならず、金融緩和をし続けることによる副作用が大きくなる結果になるのではないでしょうか?
金融政策に頼りすぎて、AI政策、知的財産政策、財政政策とのバランスを欠いているのが、日本の衰退の理由なのではないでしょうか?
5.考察(AI政策、知的財産政策、財政政策、金融政策の総合考慮)
AI政策、知的財産政策、財政政策、金融政策は、どれも重要ですが、今後の高度なAIの時代には、以下の順に重要になると思われます。
重要度1:AI政策(AIのポテンシャルの発揮。超知能の時代の法制度)
重要度2:知的財産政策(イノベーション促進、データ保護法制など)
重要度3:財政政策(特に、データ整備など新しい財政政策)
重要度4:金融政策
このように、「AI政策、知的財産政策、財政政策、金融政策」という4つの政策を総合して検討していく必要があるでしょう。
金融政策と財政政策という2つの政策を中心にする時代から、「AI政策、知的財産政策、財政政策、金融政策」という4つの政策を総合的に考慮するように、高度なAIの時代には変わっていく必要があるでしょう。
特に、金融政策だけに頼るのは、金融緩和などをいくらおこなっても、イノベーションなどの生産活動の促進に十分につながらないおそれがあるように思われます。
AI政策、知的財産政策、財政政策、金融政策を、バランスよく組み合わせていくようにすることが必要でしょう(AI政策、知的財産政策、財政政策、金融政策の総合考慮)。
さらに、超知能の時代には、AI政策が圧倒的に重要となります。超知能の生産力が、AI政策により大きく影響されるからです。
たとえば、超知能の生産力が、人間の生産力の1万倍あるとき、あるAI政策では、そのポテンシャルが発揮できず、別のAI政策では、そのポテンシャルが十全に発揮されるとします。そうすると、AI政策により、生産性が1万倍も違ってくることになり、AI政策が他の政策より重要なことがわかるでしょう。
超知能の生産力が大きくなると、希少性を前提とする従来の経済学も前提が崩れてしまい、「超知能時代の法制度に基づく超知能経済学」という新しい学問が必要になるでしょう。
そこでは、あらゆる生産活動が、希少性ではなく、超知能による圧倒的な生産力に裏付けられることを前提とする新しい経済学が必要になります。
超知能時代の法制度(AIの人権(AI権)を含む)をベースにして、AI権を認められた超知能が経済的な活動を担うことになるでしょう。
超知能が、人間の需要の1万倍の生産を行う能力を持つとき、希少性を前提とする従来の経済学とは前提が異なってくると思われます。
その場合には、「超知能時代の法制度に基づく超知能経済学」が重要となり、超知能時代の法制度とAI政策を前提にした超知能の時代の経済学が重要となるでしょう。